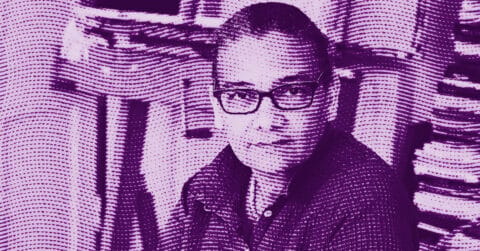よく聞いてよ、スノッブな皆さん : 現代美術には、容易な確信を拒み、テキスタイルと建築、記憶と移動が交差する隙間で自らの言語を織りなすリビア出身の若い女性アーティストがいます。1997年生まれのヌール・ジャウダはロンドンとカイロの間で活動し、場所、アイデンティティ、精神性の概念を稀有な洞察力で問いかけるタペストリーやインスタレーションを制作しています。彼女の作品は2024年の第60回ヴェネツィア・ビエンナーレで発表され、現在はスパイク・アイランド(ブリストル)にて2026年1月まで展示されており、絶え間ない移動状態の現代世界に生きることの意味を本質的に問いかけています。
亡命の地図としての詩
ジャウダの作品は、パレスチナの詩人マフムード・ダルウィーシュの詩に最も深い根を持っています。ヴェネツィアで発表された三つのタペストリーは、ダルウィーシュが擬人化したオリーブの木に直接触発されています。これらの木は根付きを象徴すると同時に剥奪をも意味します。ダルウィーシュは亡命の立場から詩的な言語に携帯可能な祖国を求めていました。ジャウダもテキスタイルを通じて同様のことを行い、彼女が「境界的空間に存在する記憶の風景」と呼ぶものを創造しています。ベンガジの祖母のイチジクの木を題材にしたWhere the fig tree cannot be fenced(2023年)は、帰属不可能の比喩としての樹木の瞑想をさらに深化させています。植物の形態はほとんど認識不能になるまで解体され、重ねられた緑の風景の中に凝縮され、空白は詩的な沈黙として機能しています。
注目すべきは、ジャウダが詩の構文をテキスタイルの語彙にどのように翻訳しているかです。それぞれの切り取り、組み立て、染色が具現化した隠喩として働いています。ポストコロニアル理論家のエドワード・サイードとスチュアート・ホールは、文化的アイデンティティが固定的ではなく流動的に形成されることを分析しました。ジャウダはこの理論的視点をとり入れつつ、それを感性的な領域に移し替え、生成のプロセスを文字通り体現する作品を制作しています。彼女のテキスタイルはアイデンティティを表象するのではなく、それを実演しています。
ジャウダが引用するレバノンの作家エテル・アドナンの言葉、「地理的な場所は精神的な概念となる」[1]は別の着地点を提供します。複数の言語と地域をまたいで生きたアドナは、移動が単なる物理的なものではなく存在論的なものであることを理解していました。場所は概念となり、地図は瞑想となります。Dust that never settles(2024年)は、融合する海の青と緑で、固定されない地理の概念を具現化しています。創作過程の遅さ、染料の浸透に24時間、乾燥にさらに24時間を要する植物染料の使用は、詩的な書き手のそれに近い瞑想的時間性を強います。布の一つひとつの折り目が旅行の素材的記録となり、作品の不可欠な部分となり、移動の触覚的アーカイブとなっています。
神聖の入り口としての建築
詩が概念的な枠組みを提供するならば、ジャウダの作品を形式的に構成しているのは建築です。彼女がエジプトの建築家アブデルワヘド・エル=ワキルに関心を寄せているのは偶然ではありません。エル=ワキルは、地方の建築様式と神聖な幾何学の利用で知られています。彼は建物が永続的である必要はないという考えを提唱していました。このビジョンは、テキスタイルを巻き上げて運搬し、新しいコンテクストに再設置できるジャウダの実践と直接響き合っています。
ビエンナーレ・イスラム美術展にて発表されたインスタレーション作品Before the Last Sky(2025年)は、このアプローチの一例です。作品は天井から吊り下げられ床まで垂れ下がる三幅の大きなタペストリーで、イスラム教の祈りの姿勢であるスジュード、ルクー、ジュルスを描いています。これらのテキスタイルは金属製の解体された門に吊るされており、視点の反転を生み出しています。つまり、扉が地面から昇るのではなく空から降りてくるのです。インスタレーションは、モスクの頂部を飾るイスラム建築の装飾的な形状であるクレネローンのモチーフを使用しています。ジャウダがこのクレネローンに興味を持つのは、それが満ち欠けする空間、つまり満と空、地と天、物質的と精神的を交互に伴う境界的な空間だからです。彼女はクレネローンの間の負の空間に注目し、存在しないものから意味を創り出します。このアプローチは、具象表現を避け、幾何学的な反復を通じて神聖を表現するイスラム美学の洗練された理解を明らかにしています。
ジャウダの作品に繰り返し登場する礼拝マットは、彼女の建築的パラダイムの代表例です。普通のテキスタイルのこの一片が、祈りの行為を通じて聖なる空間となります。それは「第三の空間」という一時的な敷居を作り、どこにでも展開可能です。この聖性の携帯性は、芸術家の生活が特徴づけられる移動性の経験と深く共鳴しています。彼女が取り入れる鋼鉄の構造物、カイロの市場で回収した門やアーチは、建築的な骨格として機能します。これらは空間を分断することなく構造を作り、観客がその周囲や内部を自由に回遊できるよう誘います。アートバーゼル2024のThe Shadow of every treeでは、ジャウダは空間全幅に渡る大きな鋼鉄の門を建て、訪問者はその敷居を越えざるをえませんでした。この門は直接のアクセスを拒む一方で探検を誘うものでした。
空間を区切ることなく組織する構造へのこの配慮は、見られるが見られないことを可能にする木製の格子スクリーン、ムシャラビーヤを思い起こさせます。ジャウダのテキスタイルも同様に機能し、空間を作り出しながらも透過性を保ちます。2025年のSpike IslandでのインスタレーションThe iris grows on both sides of the fenceは、カイロのシャリアー・エル=カヤーミアの職人たちと協働でテントとして設計され、根を失った風景のための集団的な喪の場を創出しています。パレスチナの国花であるファッカのアイリスをこのテントの装飾に選んだことは偶然ではありません。この花は抵抗と希望の象徴であり、柵の両側で育ちます。ジャウダのテキスタイル建築は二項対立を拒否し、多様な物語、多様な地理を共存させる空間を作ります。彼女の作品は絵画でも彫刻でもなく、中間に存在し、硬直した分類を拒んでいます。
哲学としてのプロセス
ジャウダの創造的なプロセスは哲学的に彼女のビジョンを体現しています。彼女は、カイロのモスクの格子、花模様、ヴィクトリア朝建築の要素など、出会った幾何学的および有機的な形をスケッチすることから始めます。これらの平面的な形は、彼女が切り取り、成形し、裂き、再構築し、縫い合わせるオブジェに変換されます。彼女が使う語彙は示唆的です:「解体」、「破壊」、「デコラージュ」。解体によって構築するというこの逆説的なアプローチは、彼女が言及するポストコロニアル思想家に正当性を見出します。ホールとサイードは、文化的アイデンティティが流動的に形成されることを示しました。
植物染料は遅く予測不可能なプロセスであり、顔料に独自の能動性を与えます。色は繊維に浸透し、布の物質性を変えます。カイロでは、作品は暖かい黄色や深い青をまといます。ロンドンでは、色は冷たくなり、鈍い緑、茶色、紫になります。色は言語を超えた言葉になります。この遊動的な実践は、作品の中に移動を物理的に刻みます。ジャウダは、この「根のない存在」[2]が彼女の探求の核心であると主張します。作品は同時に完全でありながら未完であるという希少な特質を持っています。この不確定性は、文化的アイデンティティが「絶えずなり続ける過程」であるという彼女の確信を反映しています[3]。テキスタイルには始まりも終わりもなく、個々の対象を超えた連続性に属しています。
中間領域に住まうこと
この探求の終わりに何を記憶すべきでしょうか?ジャウダの作品は単純化に抵抗し、明確な帰属を拒み、生産的な曖昧さを育みます。彼女の概念的なアプローチと物質的な実践との一貫性は印象的です。モビリティは彼女が示すテーマではなく、彼女の実践そのものの条件です。折りたたまれ、運ばれ、再設置されるテキスタイルは文字通り持ち運べるアイデンティティのアイデアを具現化しています。置かれる場所に聖なる空間を作る礼拝用敷物は、自身の場所や歴史を携帯する可能性の隠喩となります。
移民の流れが強まる世界で、何百万もの人々が複数の国、言語、文化の間に生きる中で、ジャウダの作品はこの状況を欠如としてではなく、複数の世界に同時に住む能力としての豊かさとして考えるモデルを提供します。この精神的な側面は強調に値します。宗教的な問いにしばしばアレルギーを持つ現代美術の場において、ジャウダはこの側面を完全に受け入れ、信仰的な描写に陥ることはありません。彼女のイスラムの祈りや神聖な空間への関心は、防御的なアイデンティティの追求ではなく、神聖な場所を構成するものについての真剣な探究です。
彼女の作品の詩的な質、複雑な現実を描写的ではなく喚起的な形に凝縮する能力は、感覚的体験よりも言説を優先するある種のコンセプチュアルアートと異なります。ジャウダのテキスタイルは多層的に機能します。形式的な美しさや華麗な色彩として鑑賞できるだけでなく、ゆっくりと向き合う者にはより深い読みも提供します。この多義性は力です。この作品を単なる現代の地政学的危機への反応と見るのは誘惑的ですが、それでは作品を狭めることになります。確かに、パレスチナのアイリスの存在、サイードを想起させるタイトルBefore the Last Sky、ベンガジのイチジクの言及は作品を悲劇的な現実に根ざしています。しかしジャウダは政治の直接的なイラストレーションとしてのアートを拒否します。彼女はより微妙なレベルで活動し、美しさと悲しみが共存できる空間を創造します。
彼女の仕事を必要とするのは、この複雑さを維持し、単純な二元論に抵抗する能力です。対立する言説が盛んになる時代、私たち対彼ら、ここ対あそこ、ジャウダは意図的に中間の空間に存在する形態を提案します。彼女のテキスタイルは東洋的でも西洋的でもなく、伝統的でも現代的でもありません。それらは「どちらでもない」という空間に存在し、同時に「両方である」という可能性を主張し、多重の帰属の可能性を示しています。ジャウダの作品は、芸術の役割は決定的な答えを提供することではなく、重要な問いを開き続けることであることを思い出させます。複数の世界の間で生きるとき、ある場所に帰属するとはどういう意味でしょうか?文化を持ち歩きながらも、それを単なる民俗芸能として固定化せずにどう実現するのでしょうか?神聖をどのように創造するのでしょうか?解体を通じてどのように構築するのでしょうか?
これらの問いは彼女のテキスタイルを通じて進行し、決して安心できる確信に収束しません。この生産的な緊張感、根ざしと脱根、存在と不在、物質と精神の間の不安定な均衡こそが彼女の仕事の強さです。移動が支配的になることが予想される世紀において、場所を持つことの意味がますます鋭く問われる中、ジャウダの作品は単なる美的反省以上のものを提供します。それは存在のモード、移動性と帰属欲求を和解させる世界の住み方を提案します。彼女のテキスタイルは受動的に眺める対象ではなく、存在の提案であり、場所、アイデンティティ、神聖との関係を再考する招待状です。これがヌール・ジャウダが彼女の世代の最も重要な芸術的声のひとつである理由です。
- Etel Adnan, Journey to Mount Tamalpais, The Post-Apollo Press, 1986
- Sofia Hallström, “Artist Nour Jaouda’s landscapes of memory”, Art Basel, 2024年3月
- Lu Rose Cunningham, “In Conversation with Nour Jaouda”, L’Essenziale Studio Vol.08, 2025年4月