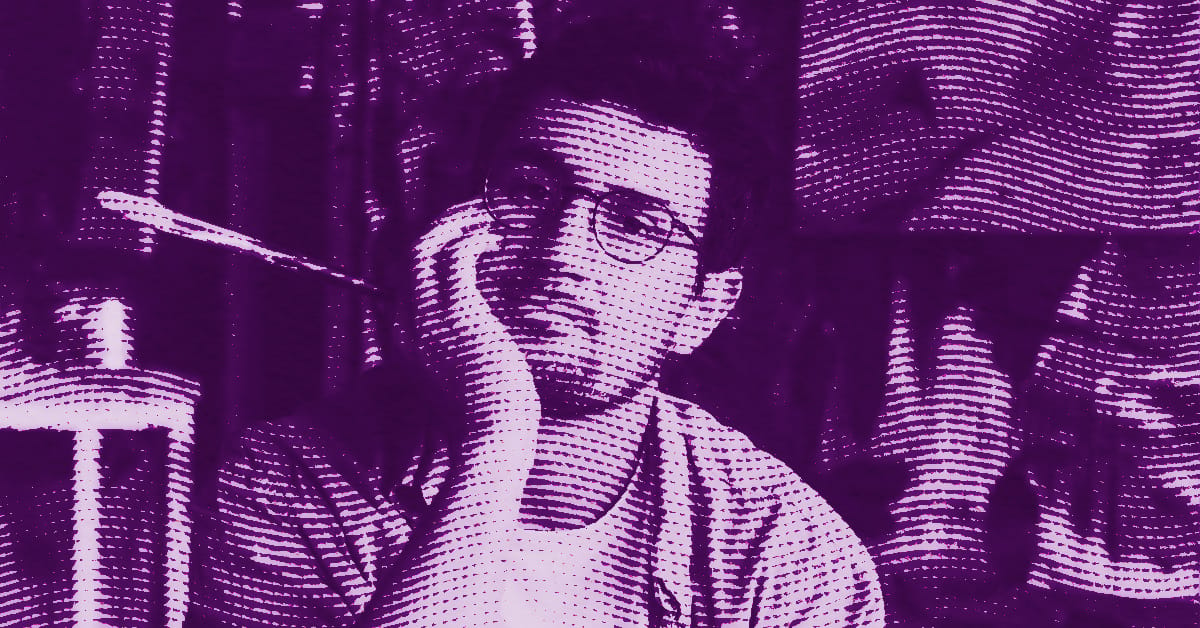よく聞いてよ、スノッブな皆さん。ルイ・フラティーノは、現代アーティストの中でほんのわずかしかいない、身体を持つことの意味を真に理解している一人です。ただ身体を所有するだけでなく、その感覚や欲望、脆さを伴って完全にその身体を生きることです。彼の作品を観ると、身体を通じた世界との関わりについて、モーリス・メルロー=ポンティの最も重要な直観を思い起こさせる現象学的な絵画表現に直面します。フラティーノは、芸術の真の使命は自身の身体性を感じさせることだと私たちに思い出させてくれます。彼の作品は単なる男性の身体やホモエロティシズムを祝福するものではありません。そうした解釈はあまりに狭義ですが、身体を持って生きることの深い探求なのです。
フラティーノの身体は決して匿名的ではありません。常に名前、歴史、親密さを宿しています。彼が「Four Poster Bed」(2021年)で描く眠る恋人や「Kissing Couple」(2019年)の抱き合う身体など、各被写体は特定性と普遍性を兼ね備えています。彼が体毛、しわ、関節などの身体的細部を扱う様子を見てください。それは解剖学を感情の地形図へと変化させるほどの注意深さです。批評家のロベルタ・スミスはこの特質を的確に捉え、『彼の絵画は「家庭で長居することの喜びの温かさ、共有された親密さに満ちています。そして絵画の注意深さと博識さも併せ持ち、鑑賞者にも同様の吟味を促します。ほとんどすべての筆致や痕跡、家具や体毛の細部に至るまで、それぞれ独自の生命を持っています。」と書いています。[1]
この身体の現象学への取り組みは、美術史において前例のないものではありません。しかし、フラティーノが際立っているのは、この関心をモダニズムの伝統に対する根本的な再評価と融合させる能力にあります。彼はピカソ、マティス、ハートリーを単に模倣するのではなく、それらを消化し、現代のクィアな経験というレンズを通じて再構成しています。マリオ・ミエリの著書「ゲイへの共産主義をめざして」から借用したタイトルの「I keep my treasure in my ass」(2019年)を見てみましょう。この作品は、芸術家が自分の肛門を通じて自らに誕生を与える姿を描いており、しばしば性的または排泄機能に還元される器官を、アイデンティティの創造と自己生成の場として表現する力強い視覚的比喩となっています。
この絵画は、第60回ヴェネツィア・ビエンナーレで展示され、フラティーノがモダニストの語彙を展開する方法を完璧に示しています。キュビスムの幾何学的な顔、表現主義的な身体の歪みを用いて、ピカソのようなモダニストでさえも、彼らの天才にもかかわらず決して表現できなかった経験を具現化しています。ある批評家はこの作品の前で「人々はほとんど列を作ってこの絵の前に立ち、その後しかめ面をしたり身体的な反応を示したりしていた」と指摘しました[2]。この本能的反応こそがメルロー=ポンティが「世界の肉」と表現したものであり、私たちの知覚と知覚される世界が相互認識の舞踏で出会う瞬間です。
メルロー=ポンティの現象学は、私たちが外部から世界を観察する脱肉化された精神ではなく、現実の織物に組み込まれた具現化された存在であることを教えてくれます。私たちの身体は他の物体の中の単なる物体ではなく、世界を持つための手段です。フラティーノはこの真実を本能的に理解しているようです。「Washing in the Sink」では、裸の男が愛の後に洗い、その平凡な行為が身体の再居住の儀式に変わります。ここで芸術家が関心を持っているのは性交行為ではなく、私たちが身体性を完全に意識し直すその後の瞬間です。
メルロー=ポンティは『目と精神』で「画家は『自分の身体を持ち込む』とヴァレリーは言う。実際、精神がどうして絵を描けるだろうか。画家は自分の身体を世界に貸与することで、世界を絵に変える」と書いています[3]。フラティーノは間違いなく各絵画に自分の身体をもたらしており、それはナルシス的な行為ではなく現象学的な奉納としてのものです。彼の絵画技法自体、厚みのある絵の具の物質性、質感豊かな筆致、地の暖かみと海の冷たさを交互に用いるパレットは、身体の経験に対するその関心を反映しています。
この現象学的アプローチは、明示的なエロティックな場面を超えて、具現化された存在のあらゆる側面を包含します。フラティーノの静物画、『My Meal』(2019年)や『Polaroids on the kitchen counter』(2020年)なども同様の感受性を示しています。日常の物体、トーストにのった卵、チェリートマト、散らばるポラロイド写真が、裸の身体と同じ愛情深い注意で描かれています。メルロー=ポンティもフラティーノも、身体とその宿る世界との間に本質的な分離はなく、両者は現実の同じ肉体的な織物に織り込まれていると考えているからです。
「私は絵が硬く、厚く、身体的なことが好きです」と作者は語ります[4]。この言葉は、単なる表象ではなく具現化としての絵画への彼の取り組みを明らかにしています。彼の作品は単に身体を描いているのではなく、自らがそれぞれ独自の質感、重み、存在感を持つ身体そのものとなっています。
フラティーノがメルロー=ポンティと共有しているのは、私たちの世界との関係が根本的に前反省的であり、知的分析の前に感覚的知覚に根ざしているという確信です。私たちが『Metropolitan』(2019年)を観るとき、身体が圧縮された空間で絡まり合うゲイバーのシーンを、単にクィアな社交性の表象として「読み取る」のではなく、その経験の温かさ、親密さ、質感を身体的に感じ取ります。この作品は、純粋に認知的な解釈を飛び越えて、直接私たちの身体に語りかけます。
しかし、メルロー=ポンティの現象学は単なる知覚の理論ではありません。それはまた相互主観性の理論でもあります。私たちの身体は世界へのアクセスを可能にするだけでなく、他者を私たちと同じく具体化された主体として認識することを可能にします。この相互主観的な次元こそが、フラティーノが恋人や友人の肖像画で探求するものです。『Me and Ray』や『Tom』の中で、視線は決して対象化するものではなく、常に他者を自身の内面性を持つ具現化された主体として認めています。
メルロー=ポンティが『知覚の現象学』で書いているように:「他者の身体は私にとって対象ではなく、また私の身体も彼にとって対象ではない……それは身体であることの別のあり方である。」[5]フラティーノの絵画の人物たちは決して欲望の対象に還元されず、常に神秘性と自律性を保持しています。最も露骨に性的なシーン、例えば『Kiss』で一方の男性がもう一方の肛門愛撫を行っている場面でさえも、他者を主体として認めています。
この相互主観的な認識は、性的パートナーを超えて家族にも広がります。『My sister’s boys』では、フラティーノは暗い扉に囲まれた裸の2人の少年を描いています。この作品は警戒心が強い私たちの文化では誤解されやすいかもしれませんが、タイトルが示す通り、彼らは甥っ子たちです。フラティーノはこのように描くことで、子供の裸に対する過剰な性的見做しを拒否しつつ、子供たちも具体化された存在であることを認めています。恋人、友人、子供といったすべての具体化の形態の連続性を確立し、それらを同一視することなく扱っています。
この現象学的アプローチは、「Satura」展が開催されているイタリアの状況で特に響きを持ちます。右派政府ジョルジャ・メローニのもと、同性愛者の親に対する厳しい制限が課され、レズビアンの母親の一部が子供の出生証明書から除かれる事態が起きている国において、フラティーノの絵画は現象学的抵抗の行為となります。彼らは身体経験が国家や宗教によって課されたカテゴリーを超越することを主張しています。
フラティーノ自身もこの政治的な次元を認めながら、それを明確なメッセージに還元することを拒んでいます。「イタリアの政治状況を知っていて、クィアの人々が家族を持つのがどれほど難しいかを感じて、多くのプレッシャーを感じていました。自分の立場をはっきり示す何かを作る責任があったのかもしれません。しかし結局、私はそういう描き方はしません。直感的または無意識的に作品を創造し、その視点がはっきりしていることはありません。それは体験された人生の中にいることの問題なのです。」[6]
この「体験された人生」へのこだわりは、イデオロギー的立場よりも、深く現象学的です。メルロー=ポンティにとって、経験は常に理論化に先行し、私たちの世界への存在はそれを概念化しようとする試みよりも常に豊かで曖昧だからです。同様に、フラティーノの絵画は政治的文脈に必然的に位置づけられても、決して政治的メッセージに還元されることはありません。
フラティーノはこのアプローチによって時折批判を受けることがあり、とりわけトランスジェンダーや人種的少数者の表現が不足していると指摘されることがある。彼の応答は示唆的である:「絵画には観客がいるが、私が制作しているときには存在しない。私自身に語りかけているので、自分のアトリエという世界で最も私的で神聖な場所においては、コミュニティという考えに対して責任を持つ必要はない。」[7]このアトリエを現象学的に最も基本的な空間として位置づけ、芸術家が自身の経験と身体的対話を交わす場としての主張は、メルロー=ポンティの思想と深く共鳴する。
哲学者と芸術家の双方にとって、真理は世界に課される抽象的な構成物ではなく、私たちの身体的関与から生まれる啓示である。フラティーノは「直感的または無意識的に」働き、身体が描く世界との対話を重視し、あらかじめ定められたビジョンを押し付けない。彼が説明するように:「絵を描くのは楽しみであり、そのままでありたい。どのように肌を描く?どのように木を描く?ある葉と別の葉とはどのように違う?それは純粋な色彩であり、質感であり、その謎を解くことに大きな喜びを感じている。」[8]
絵画の「謎」を解く喜びは、メルロー=ポンティが「絵画の問いかけ」と呼んだものを思い起こさせる。これは視覚芸術が概念的哲学にはできない可視の問いを投げかける方法である。フラティーノが肌や木の表現方法を模索する際、それは単なる技術的課題ではなく、それらの物質の本質や、生きた意識に現れるあり方についての存在論的な問いである。
批評家のダーガ・チュー=ボーズはこの特徴を捉えて「フラティーノの官能への月光のような視線は、別の視点では平凡に見える詳細に集中している」と記述している。[9]この感覚的な詳細への注意は、平凡を啓示へと変えるという現象学的アプローチの核心である。メルロー=ポンティにとって、知覚の奇跡はまさに平凡の中に非凡を明らかにし、まるで初めて世界を見るかのように私たちに見せる能力である。
フラティーノはこの変容された日常への魅力を共有している。彼の家庭的な場面、朝食、休息、読書の絵画は、日常を超越しながらもそれから切り離さない存在感を帯びている。『Garden at Dusk』(2024年)では、一人の男性がテーブルでうたた寝をし、もう一人が背景で花の世話をしている。この一見平凡な光景は、身体的な世界の住まい方の異なる形態についての瞑想となっている。片方は眠りへと身を任せ、もう片方は植物への触覚的関与に没頭している。
この日常の変容は、フェルメールからボナールに至る絵画の長い伝統に位置づけられ、フラティーノもこれを影響として認めている。しかし彼が際立っているのは、この伝統に現代的なクィア感性を注入し、それを単なるアイデンティティ政治に還元しない点である。ハリー・タフォヤの観察によれば、彼の絵画は「形式的な問題にとらわれるよりも、代替的な存在状態の衝動的な一瞥を捉え、それらを光へと追い求める陶酔に関わっている」。[10]
この光への追及はフラティーノの多くの作品に文字通り表れており、自然光が大きな役割を果たしている。『Waking up first, hard morning light』(2020年)では、朝の太陽光が日常的な場面、眠る男性を現象学的な啓示に変えている。この光への関心は、メルロー=ポンティがセザンヌの絵画について述べた考察を想起させる。そこでは光は単なる光学現象ではなく、「世界の肉体」の顕在化である。
フラティーノにとって、この光は個人的かつ地理的に特定の質を持っている。彼は「夏の間ずっと、その光はメリーランドの光なんだ」と言い、故郷の州を指している。[11] この観察はメルロー=ポンティが「スタイル」と呼ぶものと響き合っている。つまり、それぞれの身体が世界にどのように独自に住み、知覚するかという独特の方法だ。我々の知覚は決して中立的でも普遍的でもない。常に我々の経験した歴史、記憶、知覚習慣によって色づけられている。
メルロー=ポンティの「スタイル」という概念はまた、フラティーノの折衷的な絵画アプローチを理解する助けにもなる。彼の作品はモダニストの影響、ピカソ、マティス、ハートリー、デ・ピシスを自由に混ぜ合わせているが、決して模倣や無意味な引用には陥らない。これらの影響は完全に吸収され、彼自身の「知覚的スタイル」によって変容されている。彼が説明するように、「私は絵画とはいつでも以前に見たものを再解釈、あるいはリサイクルすることだと思います。私の場合、特にモダニズム、ピカソやマティスの構図や主題を借りたいのですが、知っている人々のように人物を再想像しています。」[12]
この再想像はモダニストの語彙を根本的に変えている。ピカソのキュビスムの身体はしばしば女性の身体の過酷な客体化に特徴づけられるが、フラティーノにおいては男性同士の相互認識の場となっている。オリエンタリズムのオダリスクは、現代のゲイ男性が自分自身の居住空間の中で再構築され、異性愛的男性の視線の伝統を覆している。ジョセフ・ヘンリーが指摘するように、「もしゲイの感性がモダニズムを無傷のまま保つなら、クィアな変種はその欠点に挑み、その戦略を最大限に活用し、あるいはモダニズムを単なる歴史的カテゴリーに追いやる。」[13]
フラティーノはこれらの立場の間を揺れ動き、時にモダニズムを無傷で保ち、時に根本的に覆す。しかし一貫しているのは、日常の身体的現象学に対する彼の献身だ。彼の絵画は単なるスタイルの演習や美術史に関する知的なコメントではなく、常に生きた経験に根ざしている。
メルロー=ポンティが書いたように、「現象学的世界は先行する存在の明示ではなく、存在の基礎である。」[14] 同様に、フラティーノの絵は既存の現実の説明ではなく、新たな存在の可能性が生まれる知覚的世界の創造だ。彼の裸の男性たちは単に現代ホモエロティシズムを「表象」しているわけではない。彼らは男性間の欲望が世界内存在の正当な様相となる現象学的空間を構築している。
この現象学的基盤こそが、フラティーノの作品が強烈な反応を引き起こしてきた理由を説明している。肯定的なものも否定的なものも含めてだ。アイオワ州デモイン美術館で予定されていた展示は、彼が「New Bedroom」を含めることを主張し、二人の裸の男性が性的関係を持つ様子を描いたために中止となった。彼が驚いたのは潜在的な侮辱ではなく、「そうした恐れがあるということだった。私はそれを本当に悲しいと思う。なぜなら、それはおそらくこれを祝福したかもしれないコミュニティに対する非常に低い期待を示していたからだ。」[15]
この逸話は、身体的な芸術が確立された規範を乱す持続的な力を示している。ますます仮想的で脱身体化された文化の中で、身体的経験が商業化されたり消去されたりしている場所で、フラティーノのあくまで肉体的な絵画は現象学的抵抗の行為となっている。それらは身体が、その性的、官能的、社会的特異性において、我々の世界内存在の根源的な場であることを主張し続けている。
この抵抗は単なる政治的またはアイデンティティの問題ではなく、存在論的なものです。メルロー=ポンティは『知覚の現象学』の中でこう書いています:「私は自分の身体の前にいるのではなく、身体の中にいる、いやむしろ私は身体そのものだ。」[16] この過激な宣言は、フラティーノの絵画が私たちに認識するよう促すことを完璧に要約しています。それは、私たちは身体から離れた精神として自分の身体を観察しているのではなく、すべての経験が私たちの身体的存在によって形作られ、可能になっている根本的に身体化された存在であるということです。
デジタル仮想性と概念的抽象性がますます私たちの経験を支配する世界で、この現象学的認識はほとんど革命的な行為となります。フラティーノの絵画は、肉体、質感、光、そして身体的親密さの官能的な祝福を通じて、私たちが物質的世界への繋がりからあまりにも離れてしまったときに失いかねないものを思い出させてくれます。
しかしそれだけでなく、絵画はより完全に身体化された存在とは何かというビジョンも提供します。それは、快楽、優しさ、感覚的好奇心、そして相互主観的認識が例外ではなく標準となる存在です。アーティスト自身が書いているように:「絵画の中で美しい人生の探求があり、私はその探求に近づくために絵画を使っていると思います。」[17]
世界との現象学的関与を通じた「美しい人生」の探求は、メルロー=ポンティの哲学的プロジェクトと深く共鳴します。彼にとってもフラティーノにとっても、目標は単に世界を理論化し表現することではなく、より完全に、より意識的に、より官能的にその世界に住むことです。
ルイ・フラティーノの絵画は、私たち自身の肉体を、所有する対象ではなく、世界を持つための手段として再発見するように私たちを招きます。私たちの身体は単なる感覚の容器や欲望の道具ではなく、私たちの存在の場であり、私たちと世界が出会い、相互に創造し合う地点であることを思い出させてくれます。抽象的な概念化や表面的な挑発によってしばしば支配される芸術の風景の中で、この現象学的招待はフラティーノが現代美術に対して提供する最も貴重で持続的な貢献かもしれません。
- ロベルタ・スミス、『”ルイ・フラティノ”』ウィキペディアより。
- アレックス・ニーダム、『”年をとってゴツゴツになった自分を描くのが待ちきれない”: ルイ・フラティノの官能的な世界』、アーティストインタビュー。
- モーリス・メルロー=ポンティ、『”目と精神”』ガリマール社、1964年。
- サイモン・チルバース、『ルイ・フラティノは親密になりたいと思っている』、フィナンシャル・タイムズ、2024年9月27日。
- モーリス・メルロー=ポンティ、『”現象学的認識論”』ガリマール社、1945年。
- アレックス・ニーダム、『”年をとってゴツゴツになった自分を描くのが待ちきれない”: ルイ・フラティノの官能的な世界』、ガーディアン、2024年10月29日。
- 同上。
- 同上。
- ダルガ・チュウ=ボース、『オープニング:ルイ・フラティノ』、アートフォーラム、2021年3月。
- ハリー・タフォヤ、『内面が輝く友人や恋人たちの絵画』、ハイパーアリジャー、2019年5月16日。
- ダルガ・チュウ=ボース、『オープニング:ルイ・フラティノ』、アートフォーラム、2021年3月。
- ステファノ・ピロヴァーノ、『注目すべき若手アーティスト:ルイ・フラティノ』、コンセプチュアル・ファイン・アーツ、2018年2月20日。
- ジョセフ・ヘンリー、『愛と孤独:具象絵画におけるモダニズムのクィア化』、モムス、2019年8月1日。
- モーリス・メルロー=ポンティ、『”現象学的認識論”』ガリマール社、1945年。
- アレックス・ニーダム、『”年をとってゴツゴツになった自分を描くのが待ちきれない”: ルイ・フラティノの官能的な世界』、ガーディアン、2024年10月29日。
- モーリス・メルロー=ポンティ、『”現象学的認識論”』ガリマール社、1945年。
- アレックス・ニーダム、『”年をとってゴツゴツになった自分を描くのが待ちきれない”: ルイ・フラティノの官能的な世界』、ガーディアン、2024年10月29日。