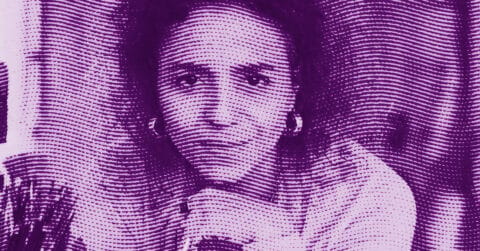よく聞いてよ、スノッブな皆さん。今こそ、我々の時代の矛盾を最も体現するアーティストについて語る時です。松山智一は単なる無味乾燥なあなたの部屋のための魅力的なイメージの製造者ではありません。いいえ、このブルックリン出身の日本人は、西洋のポップ美学と日本の絵画伝統を組み合わせ、宇宙的なDJが一見相容れないサンプルをミックスし、驚くべき調和を生み出すかのように融合させています。
松山の特大キャンバス作品を初めて見た時、私は最初、安直なエキゾチシズム、裕福なコレクターが多様性を求めて喜ぶ既製の多文化主義のまた別のバージョンだと思いました。なんという大きな誤りでしょう!松山ははるかに繊細で深遠なゲームを演じており、この単純な解釈をはるかに超えています。
彼の無表情な顔立ちのキャラクターが、花柄や幾何学模様で溢れた豪華な室内空間を漂うのを初めて見た時、私は即座にホミ・K・バーバの文化的混成性に関する著作を思い出しました。そうです、このインドのポストコロニアル理論家は、アイデンティティが “第三の空間”、つまり文化が出会い交渉し相互変容する隙間で構築されることを教えてくれました[1]。松山の作品は、そのオリエントか西洋か、伝統的か現代的かに分類されることを拒むことでこの理論を完璧に体現しています。
1976年に日本の高山で生まれた松山は、日本と南カリフォルニアの間で育ち、2000年代初頭にニューヨークに定住しました。この絶え間ない根無し草的経験が彼の作品の中心にあります。アーティスト自身はこう語っています:「私は故郷を持ったことがありません。アメリカに4年間住んだ後、12歳で日本に帰国したことは、アメリカに移住した時よりも文化的ショックが大きかったです」[2]。この永遠の異邦人としての立場を、松山は創造的な力、世界のグローバル化におけるアイデンティティに関する絶え間ない問いとして変換しました。
彼の絵画で私が印象に残るのは、江戸時代の日本の版画から採られた柄と、現代のポップカルチャー、ブランドのロゴ、プリント生地といったリファレンスをどのように並置しているかという点です。2023年の「You, One Me Erase」では、フリーダ・カーロの自画像、ダイアン・アーバスが撮影した象徴的な双子、キース・ヘリングの姿、バーバラ・クルーガーの作品「Your Body is a Battleground」が共存する、本当の意味でのポストモダンな好奇心のキャビネットを創り上げています。中央には、カラヴァッジオの「ホロフェルネスの首をはねるユディト」をサイケデリックに再解釈し、蛍光色で爆発させたものがあります。この過激な継承は混沌として見えるかもしれませんが、松山はこの乱れを外科的な正確さで演出しています。
バーバは「文化的ハイブリッド性は、認識できない何か新しい、異なるものを生み出し、意味や表象の新しい交渉の場となる」と指摘しています[3]。これはまさに、松山がファッション雑誌のイメージとヨーロッパ・ルネサンスから着想を得た構図、伝統的な日本のモチーフを混ぜ合わせる時に行っていることではないでしょうか?彼は単に異質な要素を並べるだけでなく、これらのインスピレーションの源を超越した新しい視覚的言語を創造しています。
松山の作品は、私たちが常に異なる文化、時代、文脈からのイメージにさらされているインターネットの時代にこそ、一層重要性を増します。バーバが指摘するように、「境界は何かが現れ始める場所となる」[4]のです。松山はまさにこの境界、つまり文化的アイデンティティが絶えず交渉され、再定義されるリミナルな空間に位置しています。
例えば「Fictional Landscape」シリーズでは、伝統的な日本の柄があしらわれた現代的な服を着たアンドロジナスな特徴を持つ人物たちが、西洋のブルジョアの室内と日本の衝立を同時に想起させる背景に置かれています。しばしば虚ろな目を持つこれらの人物は、定義されない時空間に浮かんでいるようで、異なる文化的現実の間に宙吊りになっているかのようです。彼らはバーバが「意味や文化的アイデンティティが優位も強制もされずに交渉される」スペースと呼んだ「間」に生きています[5]。
松山の作品を単なる文化の多様性の祝福、多文化主義のユートピア的ビジョンと見るのはあまりにも簡単すぎます。いいえ、彼の作品はもっと曖昧で複雑です。地理的・文化的境界がますます曖昧になる世界で、私たちが自分自身をどのように定義するかという根本的な問いを投げかけています。バーバは説明します。「発話の分裂した空間の理論的認識は、多文化主義のエキゾチシズムや文化の多様性ではなく、文化のハイブリッド性の刻印と表現に基づく国際文化の概念化への道を開くかもしれない」[6]。
この文化的ハイブリッド性の概念は、松山が作品の中でモチーフやテキスタイルを扱う方法で特に顕著に現れます。インタビューで彼はこう述べています。「私はモチーフやテキスタイルのデザインに興味を持ちました。なぜなら、それらは言語的ではないからです。鳳凰や龍のようなものを見ると、瞬時に文化を感じ取れます」[7]。しかし松山はそれらのモチーフを単に再現するのではなく、変容させ、再結合し、他の文化的リファレンスと対話させています。これにより、私たちが特定の文化に属すると考えるシンボルは、実際には何世紀にもわたる交流と影響の結果であることを示しています。
シルクロードは、松山が指摘するように、エジプト、中国、そして世界の他の地域との間でモチーフや芸術技術の交流を可能にしました。”各文化は、数十年または数世紀にわたって自分たちに留まった情報は自分たちのものだと主張する”[8]と彼は皮肉を込めて観察しています。彼の作品は、文化的真正性という概念自体が問題を孕んでいること、文化は常に動いており、絶えず変化していることを私たちに思い出させます。
この考察はバーバの言葉とも重なります。彼はこう書いています:「文化とはそれ自体で単一的なものでは決してなく、自己と他者の関係においても単純に二元的ではない」[9]。松山は、彼の絵画にウィリアム・モリスや日本のモチーフなど様々な伝統からの要素を取り入れることで、異なるアイデンティティと文化の重なりを生み出しています。これはアメリカ的でもイギリス的でもアジア的でもなく、ユートピア的なグローバリズムを語る方法です。
私は特に松山が彼の絵画の形そのものを遊ぶ方法が好きです。彼の絵画は単なる長方形ではなく、しばしば異なるサイズの複数のキャンバスで構成されており、不規則に組み合わされ、描かれた内容に合わせて縁や輪郭が切り取られています。このアプローチはバーバが「文化的差異のパフォーマティビティ」と呼ぶものを連想させます[10]。それは、文化的アイデンティティが固定的な存在ではなく、行動と相互作用の中で定義される絶えず変わり続ける構築物である方法を示しています。
松山の彫刻作品は、アイデンティティと認識についてのこの考察をさらに深めています。ステンレス鋼の鏡のように磨かれた作品は、周囲の環境と鑑賞者を映し出します。アーティストはこう説明しています:「作品はその環境を吸収しており、それは人が周囲の文化を吸収する様子の比喩です」[11]。これらの彫刻は親しみがありながらも異質で、私たちが実際の生活でではなく夢を通じて知っている世界を想起させます。
バーバは私たちにこう考えるよう促します:「文化的アイデンティフィケーションの問題は、あらかじめ与えられたアイデンティティの肯定でも、『伝統』文化の達成でもなく、文化的差異の表現プロセスそのものである」[12]。松山の作品はこの考えを完璧に例証しています。彼の登場人物はしばしばアンドロジナスで、現代的なファッションと伝統的な着物の両方を思わせる服を着ています。彼らは絶え間なく構築されるアイデンティティを体現しており、単一の伝統への所属によってではなく、複数の文化的影響の間を行き来することによって定義されます。
2021年に発表された「The Best Part About Us」シリーズにおいて、松山は「世界的な私たち」と呼ぶものを作成することで、この考察をさらに深めています。彼の登場人物は若く、美しく、豪華な服を着ていますが、まるで夢遊病者のように方向感覚を失っています。彼らはすべてを手に入れながらも帰属感や自分が誰であるか、何をすべきかの明確な理解を欠く恵まれた若者たちを体現しています。彼らはバーバが「現代のポストコロニアルな状態」と呼ぶものを表しています。それは「疎外を超えた異質性、非帰属の感覚であり、混成的な主体性の一形態となる」[13]という特徴を持っています。
松山の作品で特に興味深いのは、文化的ハイブリッド性の概念を伝えるために彼が色彩を用いる方法です。彼の鮮やかでほとんどサイケデリックなパレットは、日本の絵画伝統にも西洋の慣習にも当てはまりません。むしろ、それらはこれらのカテゴリを超越した独自の視覚世界を創り出しています。ババが指摘するように、「文化的ハイブリッド性は単なる内容やテーマの問題ではなく、形態やスタイルの問題でもある」[14]。
松山の創造的プロセス自体がこのハイブリッド性の象徴といえます。ニューヨークのプラット・インスティテュートでグラフィックデザインを学び、自ら絵画を独学で習得した彼は、伝統的な技法と現代のデジタルツールを組み合わせた独自のアプローチを発展させました。彼はまず、自身の二つの世界の既存のイメージを巡り、ファッション雑誌や広告をめくって現代西洋の視覚要素を探し、歴史的な文献を研究してもっと古く伝統的な日本の視覚的手掛かりを探します。多様な素材から、ファッションモデルを思わせる人物が伝統的な日本の衣服に似た服を着ており、背景には幕府時代の屏風を思わせる現代都市のゴミが散らばる光景が融合したシーンを形作ります。
この作業方法は、ババが言う「文化的翻訳」を連想させます。これは「一方でも他方でもなく、文化的交渉の過程に介入するそれ以外の何かな要素」[15]によるものです。異なる文化的伝統からのばらばらな要素を融合することで、松山は単なるポストモダンなコラージュを作るのではなく、新しい意味や解釈の可能性を生む真の文化的翻訳を創造しています。
松山の芸術は、私たちに通常のカテゴリーを再考し、文化的アイデンティティの本物とは何かについての前提を問い直すことを促します。ババが指摘するように、「ハイブリッド性は文化の境界が過去対現在、伝統対現代の単純な問題ではないことを浮き彫りにし、それは現在進行中の絶え間ない交渉過程である」[16]。
松山の絵画における室内空間は特に興味深いものです。Elle DecorやArchitectural Digestなどのデザイン雑誌に触発されることが多く、西洋の社会的・経済的成功を連想させる豪華な室内を表しています。しかし松山は、そこに自然の要素(鳥、蝶、植物)と伝統的な日本のモチーフを導入して変容させます。これにより、完全に西洋でも東洋でもない、新しく独自のハイブリッドな空間が生まれます。
この手法は、ババのいう「第三の空間」に関する考察を想起させます。これは「文化の意味や象徴には統一性や固定的な本質がなく、同じ記号でさえも取り込まれ、翻訳され、歴史的に再解釈され、読み直されうる」[17]とされる文化的交渉の領域です。松山の室内はまさにそのような第三の空間であり、さまざまな文化的伝統が出会い互いに変容しあう場所です。
彼の作品で特に印象的なのは、私たちの期待や文化的偏見と遊ぶ方法です。彼は高尚な文化(カラヴァッジョ、マティス、日本の伝統絵画)への言及と、大衆文化の要素(ブランドのロゴ、マンガのキャラクター)を混ぜ合わせ、これら異なる文化表現の形態間の従来の階層を問い直しています。バーバが指摘するように、”文化のハイブリディティは、自己/他者、東/西、第一世界/第三世界の二極から離れて文化的アイデンティティのモデルを再考せざるを得なくさせる”[18]。
今日では文化的資格取得に関する議論が絶えない中、松山の作品は微妙で複雑な視点を提供しています。単に他の文化の要素を取り込むだけでなく、異なる伝統間の対話を生み出し、それらの相互影響と絶え間ない進化を認識することなのです。バーバは説明します、”ハイブリディティは矛盾を排除する問題ではなく、それらと交渉することだ”[19]。
松山が描く人物はしばしば性別において曖昧で、男性的特徴と女性的特徴を組み合わせています。この曖昧さはバーバが言うところの”植民地的言説の両義性”を反映しており、それは植民地的アイデンティティが常にある種の不安定さ、流動性を帯びていることを示しています[20]。松山は伝統的な二元類型を超える人物を創り出すことで、より流動的で複雑なアイデンティティを想像するよう私たちを促しています。
彼の作品で特に私が気に入っているのは、視覚的に魅力的でありながら概念的に厳格な芸術を生み出す方法です。彼の作品は美しいですが、それだけでなく現代世界の課題に関する深い思考に根ざしています。バーバが強調するように、”芸術は単に社会的現実を映し出すだけではなく、それを積極的に構築し変革に参加している”[21]。
松山の仕事はバーバが”文化的移行の芸術”と呼ぶものの代表例であり、異なる文化、異なる伝統の間の辺縁的な空間から生まれる芸術です[22]。さまざまな異なる文化的伝統の要素を融合させることで、松山は従来のカテゴリーを超越し、私たちにアイデンティティや文化的帰属意識の概念を再考する新たな視覚的空間を創り出します。
民族主義やアイデンティティの閉塞感がますます顕著になる世界において、松山の作品は排除によらず対話と交流によって構築されるアイデンティティの代替的なビジョンを提供します。バーバが書くように、”文化的差異は先天的な一民族の自由な表現とは理解されるべきではなく、それは発話の瞬間に成立する文化的権威の交渉である”[23]。
松山の架空の風景はこのように文化交渉の場であり、異なる伝統や影響が出会い、相互に変容し合う場所です。それはバーバが”現代の断続的時間性”と呼ぶものであり、私たちの現代経験が異なる時間性、異なる歴史の共存によって特徴づけられていることを示しています[24]。
今日において松山の作品が特に重要なのは、バーバが呼ぶところの”広がり”、つまり私たちの時代を特徴づける世界中への人々と文化の拡散の経験を捉える能力にあります[25]。彼の作品は、彼のように異なる文化、異なる伝統、異なる言語の間で生きるすべての人々に語りかけています。
松山の芸術は、文化的アイデンティティが永遠に固定されたものではなく、常に構築され、動き続けていることを思い起こさせてくれます。真の理論的かつ政治的進歩は、伝統的な創設物語を超えて、多様な文化が出会い、交流する中で生まれる創造的な瞬間に焦点を当てる能力にあります。松山の作品はまさにこの必要性を完璧に具現化しています。彼は私たちに伝統的なカテゴリーの枠を超えて考え、世界での新しい存在の仕方、自分たちを定義する新しい方法を想像するよう促します。彼の芸術は、異なる文化や伝統の対話から生まれる美しさと豊かさを私たちに思い出させてくれます。
ですから、次に松山智一の作品に出会ったとき、その形式美や技術的な卓越さをただ鑑賞するだけでなく、彼が創り出す複雑で魅力的な世界に浸る時間を持ちましょう。その世界では文化の境界がぼやけ、新しい可能性や新しいアイデンティティが生まれます。松山の芸術は私たちの確信を再考し、現代世界の複雑さと曖昧さを受け入れるよう招きます。その視覚的な美しさを超えて、人間とは何かをグローバル化した世界の中で新しく刺激的に考えさせてくれる芸術です。だからこそ、スノッブな皆さん、松山智一に注意を払うべきなのです。それは彼が流行だからでも、彼の作品があなたのサロンに合うからでもなく、彼には私たちの時代と私たち自身について重要なことを伝えるものがあるからです。
- Bhabha, Homi K. 文化の場所:ポストコロニアル理論、ペイヨ、2007年。
- Tomokazu Matsuyamaのインタビュー、Design Scene、2016年4月。
- Bhabha, Homi K. 文化の場所:ポストコロニアル理論、ペイヨ、2007年。
- 前掲書。
- 前掲書。
- 前掲書。
- トモカズ・マツヤマのインタビュー、アルミン・レシュ・ギャラリー、2023年。
- 同上。
- バーバ、ホミ・K. 文化の場所: ポストコロニアル理論、ペイヨ、2007年。
- 同上。
- トモカズ・マツヤマのインタビュー、カヴィ・グプタ・ギャラリー、2021年。
- バーバ、ホミ・K. 文化の場所: ポストコロニアル理論、ペイヨ、2007年。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。
- 同上。