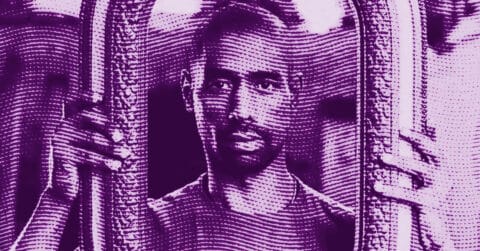よく聞いてよ、スノッブな皆さん、私は現実を誰よりも溶かす画家について話します。フィリップ・コニエは単なる才能あるアーティストではなく、イメージの外科医であり、現代の世界が自己の平凡さに溶け込むちょうどその接点で活動する絵画の放火犯です。この男が、他の人々が筆を振りかざすようにアイロンを手にし、同世代のフランス人アーティストの中で最も重要な一人となったのは偶然ではありません。
彼の技法は、まったく独特で、視覚的な破壊の一形態に似ています。彼は世界を写真に撮り、それらの画像をキャンバスに投影し、蜜ろうと顔料の混合物で丁寧に描きます。そしてここが重要な瞬間ですが、全体をビニールフィルムで覆い、アイロンでそれを攻撃します。熱で蜜ろうが液化し、イメージが歪み、丁寧に再現された現実が溶け出し、滑り、自己の幽霊へと変貌します。まるでコニエが記憶がライブで消え行く様子を示す装置を発明したかのようです。
この技法はただの署名ではなく、哲学的な立場です。イメージに窒息するまで爆撃される時代に、コニエは呼吸し、血を流し、汗をかくイメージを私たちに提供します。1990年代に彼が描いた冷凍庫を思い出してください、日常生活の白い記念碑が幽霊の墓所に変わっています。あるいは資本主義のもとで私たちが交わる近代の大聖堂であるスーパーマーケット、彼の視点によって奇妙でほとんど抽象的に見えます。コニエは日常を溶かして、その残酷な詩、そして不気味な脆さを明らかにします。
それが次の展覧会である2025年3月8日から5月10日までパリのテンプロン・ギャラリーでの「分断された風景」へと繋がります。街の環境を数十年にわたり解剖してきた後、コニエは森、野原、海に目を向けます。しかし穏やかな風景画など想像しないでください。これらの新作は自然と技術、永続と消滅が衝突する闘技場です。
コニエの芸術はガストン・バシュラールの哲学と見事に対話します。バシュラールにとって、物質は単なる対象にとどまらず、創造的想像力の積極的なパートナーです。火の精神分析で、バシュラールは「人間は火の創造者である」と書いています[1]。この観察はコニエにぴったりであり、彼の創作過程は文字通り熱を用いて物質を変容させます。これは単なる技術ではなく、世界との関係を示す生きた比喩です。バシュラールが指摘するように、火は「内面であり普遍である」[2]、まさにコニエの主題は深く個人的でありながら集合的な原型の間を揺れ動きます。
この物質の弁証法こそがコニエの作品の核心です。彼が森を描くとき、それは単純に自然を表現するのではなく、自然そのものが、すでに表象で飽和した私たちの文化におけるイメージであることを探求しています。彼の森は二重に媒介されており、まず彼が使用する写真やビデオで元画像を捉え、それから蜜ろうによる変形の過程を経ています。現れる自然は奇妙で不気味であり、加熱状態の文明の曇った窓越しに見ているかのようです。
この異化のプロセスは、哲学者マルティン・ハイデッガーが「顕現」と呼んだものを思い起こさせます。これは、芸術が単に世界を表象するのではなく、新たな方法でそれを顕現するという考えです。彼のエッセイ『芸術作品の起源』の中で、ハイデッガーは「芸術は可視的なものの再生産ではなく、可視化するものである」と主張しています[3]。コニェの作品はこの機能を完璧に体現しており、私たちの世界を再現するのではなく、それを異なる方法で可視化し、私たちがあまりにも頻繁に見過ぎて気づかなくなっているものを強調しています。
「カルカス」シリーズ(2003年)、吊るされた肉の塊は、不快でありながらも魅力的です。コニェはこれらを有機的な記念碑へと変え、私たち自身が肉の存在であることを思い起こさせる血まみれの抽象化を生み出します。このシリーズは、観客がこれらの現代のメメント・モリに囲まれるアリーナのようなものを形成します。そこには、私たちの死の運命との直接的な対峙があり、また、無菌化された文明が隠そうとする残酷な現実とも向き合うことになります。
ここにこそ、ハイデッガーの思考がコニェの作品と共鳴します。すなわち、私たちに日常的に提示される世界をそのまま受け入れないという拒絶です。現実をぼかし、溶かすことによって、コニェは私たちにそれを真に見るよう招き入れています。おそらく初めて。本書にあるように、ハイデッガーが述べる「原初の真実とは他ならぬ事物の顕現、存在の出現である」[4]という言葉は、コニェの作品全体のマニフェストとなり得ます。
ものの表面の下に隠れたものを明らかにするこの探求は、特に「列車から見た風景」シリーズ(2013年)に明白です。ここで、コニェは高速で移動する世界を、TGVの窓から捉えています。その結果は、単なる高速の風景のぼやけた表現ではなく、常に動き続ける世界における知覚そのものについての瞑想です。彼は「風景のイメージ以上に、私はその視覚における時間の経過を絵画の中に再現している」と語っています[5]。この指摘は、芸術を静的な現実の単なる再現ではなく、時間的真実の顕現として理解する点で、ハイデッガー的なものです。
しかし、コニェをドイツ哲学の視点だけで捉えるのは誤りでしょう。彼の作品は、死者の無常を表現する伝統、特に虚栄の伝統に深く根ざしています。彼の枯れた花々、つまり美しさが朽ち始める瞬間のシャクヤクやアマリリスは、この長いメメント・モリの系譜の中に位置しています。しかし、古典的な虚栄画が死を象徴する符号化されたシンボルを用いたのと異なり、コニェは世界の儚い物質性そのものを直接扱っています。
2020年の「Carne dei fiori(肉の花)」展で展示された彼の巨大な花は、単なる腐敗の表象ではなく、それ自体が絵画の物質性の中に腐敗を具現化しています。滴り落ちる蝋、変形し、ところどころ剥がれ落ちる蝋は、有機的な生命の脆弱さの完璧なメタファーとなっています。彼自身の言葉を借りれば、「これらの枯れた花々は、その生涯の終わりに達し、私たち自身の脆く儚い存在を映し出している」とのことです[6]。
この鋭い脆弱性の自覚は、彼が建築にアプローチする方法にも表れています。コニェの建物、すなわち堅固で永続的であるはずの構造物は、まるで固定された建造物の世界そのものが幻想であるかのように、私たちの目の前で溶解していきます。彼の「Google Earth」シリーズはこの論理をさらに推し進め、衛星画像の都市景観を抽象的なグラフィック配置へと変換し、暗号化された書き物のようにしています。そこにはまるで現在の考古学、つまり私たちの文明をすでに廃墟として眺めるかのような視点があります。
この考古学的な性質こそが、コニェとガストン・バシュラールの思想を真に結びつけています。バシュラールは『La Terre et les rêveries du repos』の中で、私たちの土地の物質との親密な関係、そこに私たちが夢や不安を投影する方法を探求しています。彼は「物質は私たちのエネルギーの鏡である;それは想像上の喜びで力を照らす鏡だ」と書いています〈sup〉[7]〈/sup〉。この文はコニェが単なる媒体としてではなく、創造過程で能動的なパートナーとして使用する蝋の関係を完璧に表しています。
蝋は固体から液体へ、またその逆にもなることができる物質であり、彼にとっては現実の可塑性そのものを探求する手段となっています。彼の言葉を借りれば:「蝋は魔法の物質だ…色を背景と表面の間に閉じ込めているように見える。[…] 私が気に入っているのは、それが壊れやすく繊細な物質であり、熱によって絶えず変化し、主体を消失させる可能性を内包している点だ」〈sup〉[8]〈/sup〉。ここにバシュラール的な不変性と変容、休息と行動の弁証法が正に見て取れます。
コニェが蝋を選ぶことは偶然ではありません。蝋はローマ時代のエジプトの肖像画に用いられた素材であり、この選択は歴史的な意識の深さを示し、自身の現代的な作品と人間の有限性を表現する何千年もの伝統とを結びつけています。しかし同時に、強烈に亜逆的な行為でもあります:ファイユームの肖像画が被写体の永遠のイメージを保存しようとしたのに対し、コニェは同じ技術であらゆるものの不可避な溶解を示しているのです。
保存と溶解の間のこの緊張こそが、彼の芸術的プロジェクトの核です。すべてがイメージと化し、現実そのものがメディア表象に溶け込んでいく世界において、コニェはその溶解を受け入れ統合しつつ、これを抵抗の行為に変える絵画を提案しています。世界の脆さを示すことで、逆説的に世界を表象し理解しようとする私たちの欲求の永続性を主張しているのです。
彼の作品は気候不安の時代において特に意義深いものです。テンプロンギャラリーで展示される彼の新しい風景画では、蝋画法を用いて「蝋の中に飲み込まれたかのような対象、ほとんど判別不能で、抽象へとぼかされた印象」〈sup〉[9]〈/sup〉を創出しています。これらの自然の情景は、魅惑的でありながら不安を伴い、私たちを問いかけます:脅かされる壮麗な自然をただ眺めるのか、それとも行動に移すのか。各風景は自然と人類の和解不可能な不理解を証し、気候不安に蝕まれる社会が宿る世界の美しさを祝福しています。
コニエの素晴らしいところは、批評的な緊張感を維持しながらも、目を見張る美しさを持つ作品を創り出していることです。彼の素材の扱い方にはほとんど肉体的な官能性があり、色彩や質感への明らかな喜びが、彼の題材の重みと完璧に均衡を保っています。この生産的な緊張感は、ハイデッガーが芸術作品の中の「闘争」(Streit)と呼んだ、世界と地の間の絶え間ない戦い、意味と物質の間、顕在化と隠蔽の間の葛藤を思い起こさせます。
アーティストの言葉を借りれば、「私の中には常に、間に第三の状態を見つけるために、同時に構築し破壊する意志がありました」[10]。まさにこの間に、彼の作品の力が宿っています。完全に抽象的でもなく、完全に具象的でもない;完全に世界の祝福にあるわけでもなく、その批判に完全にあるわけでもない;しかし、芸術が私たちの状況を考えるために真に必要となるこの中間領域に。
それで、はい、「Paysages fragmentés」をギャラリー・タンプロンでぜひご覧ください。そこでは、絶望に屈することなく私たちの崩壊する世界を表現する独自の方法を見出した、頂点に立つ画家を見ることができます。しばしばポストモダンのシニシズムと反動的な幼稚さとに分かれる芸術の風景において、コニエは第三の道、つまり美しさを決して手放さない批判的な関与を描き出しています。
もし行かなければ、私たちに世界がどうあるかではなく、どう壊れそして私たちの目の前で彼の視覚の熱によって再形成されるかを示す、現代フランスの最も偉大な画家の一人を見る機会を逃すことになります。
- バシュラール、ガストン。火の精神分析。ギャリマール、1938年。
- 同上。
- ハイデッガー、マルティン。どこへも通じない道。ギャリマール、1962年。
- 同上。
- コニェ、フィリップ。ギヨーム・ラセール引用。『フィリップ・コニェ、現実を超える』。メディアパール、2023年11月4日。
- コニェ、フィリップ。イザベル・カパルボとのインタビュー。『フィリップ・コニェ:Carne dei fiori、花の悲劇的で官能的な美しさ』。ArtiStikrezo、2020年6月5日。
- バシュラール、ガストン。大地と休息の夢想。ジョゼ・コルティ、1948年。
- コニェ、フィリップ。イザベル・カパルボとのインタビュー。『フィリップ・コニェ:Carne dei fiori、花の悲劇的で官能的な美しさ』。ArtiStikrezo、2020年6月5日。
- プレス資料、『フィリップ・コニェ、断片的な風景』展、ギャラリー・テンプロン・パリ、2025年。
- コニェ、フィリップ。フィリップ・ピゲとのインタビュー。『アート・インタビュー』、2021年6月。